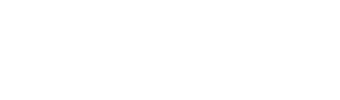奥の細道画巻 第一巻
[1-1]
「光陰は百代の過客なり」と李白がいう通り、年月は旅する者のように過ぎ去って行く。舟に乗り水面に浮かんで生涯を送る船頭や、馬の轡を引きながら老いていく馬子たちも、毎日を旅に費やして旅の中に暮らしている。昔の文人墨客も旅路で命を落とした者が多くいた。
私も何時の年からか、風に流れる雲を見ては、旅への想いを募らせ、海辺を流離い、去年の秋には深川(東京都江東区)の草庵に戻り、蜘蛛の巣を払って住んでみたりはしたが、やがて年も暮れ、春霞が立つ空に「白河の関を越えようか」と思うと、惑わす神が取り憑いたかのように心落ち着かず、道々の神が招いているかに思えて取るものも手につかない。股引の破れを繕い、道中笠の紐を付け直して、足三里のツボにお灸を据えれば、松島に掛かる月の光景が早くも心に浮かんで、住んでいた草庵を人に譲り、門人の杉山杉風の別宅に移って
草の戸も住替る代や雛の家
(こんな草庵でも住む人が替わり世も代われば、三月には雛飾りを愛でるような親子の家になることだろう)
続く連韻の表八句を草庵の柱に掛けて残した。
三月二十七日、曙の空は朧に霞み、有明の月は白みかけ、遠く富士山が幽かに見えて「上野や谷中で見た桜の花も、次は何時見られることか」と心が弱る。親しい者ばかりが昨夜から集まり、舟に乗って送ってくれる。千住(東京都足立区)という所で舟から上がると「これから前途三千里の長旅だ」との思いに胸がいっぱいになり、夢幻であるはずの世間と離れることにさえ涙が流れる。
行春や鳥啼魚の目は泪
(行く春とともに旅立つことに、鳥も鳴き騒ぎ、魚も目に涙を浮かべて、一緒に別れを悲しんでくれているのだね)
【千住】を出立する場面。右方に見送る五人、少し間を空けて左方に芭蕉と曽良との二人。見送りの五人はそれぞれにポーズを取り、何やらタガが外れたかのような哀感が漂う。一人が片手を差し上げて遠離る芭蕉たちを指差す仕種を見せ、左右の人々を関係づける。人物は細やかに描かれ、左端の芭蕉には超然とした表情までもが読み取れる。芭蕉は杖を左方に傾け、右足に重心を載せて前傾姿勢となり、歩を進めている様子を表す。
矢立の筆を執ってこれを旅の始めの句に書き留めたものの、何だか歩みが捗らない。知己の人たちは道端に立ち並んで「後ろ姿が見えなくなるまでは」と見送っているはずだ。
今年は元禄二年(一六八九)だ。「奥羽への長旅に出よう」とふと思い立って、遠い国へ旅した苦難で白髪になってしまったという故事のように、苦労を重ねるかも知れないが「耳に聞いてはいても未だ見たことの無い土地を訪ねて、そして幸い生きて帰って来られるならば」と宛ての無い望みを掛けて、この日は漸く草加の宿場(埼玉県草加市)に辿り着いた。痩せた肩に掛けた旅の荷物が早くも苦になる。ただ身軽にと出で立ったのだが、紙衣一着は夜の寒さを防ぐため、浴衣や雨具や墨と筆、そして有難く貰った餞別の品々は、さすがに捨てる訳にもいかず、道中の荷物となるのはどうにも困ったことだ。
歌枕に知られる〈室の八島(栃木県栃木市、大神神社)〉に詣でる。同行する曽良がいうには「この神は木花之佐久夜毘売といわれ、富士山の浅間大神と同一神です。(女神は戸口を塞いだ産室)『無戸室』に入り、建物を焼かれながらも貞操を誓う中に、彦火火出見尊がお生まれになったことから『室の八島』と呼ばれます。またこの歌枕に『煙』を詠み込む習わしがあるのもその謂れからです。それから、鮗という魚を焼いて食べるのを禁ずる縁起話も世に伝わっています」
三月三十日、日光山(日光市東照宮)の麓に泊まる。宿の主人がいうには「私は名を『仏五左衛門』と申します。何事も正直にと勉めておりますので、世間でこのようにいわれる通り、今夜のご宿泊も寛いでお休みください」という。「一体どんな仏様がこの俗悪な世に現れて、我等のような取るに足らない旅の者を助けてくれるというのだ」と気になり、主人の様子を目に留めていると、実際ただ愚直にも正直一途な人物だった。全く『論語』にいう「剛毅木訥、仁に近し」の通りで、生まれつきの清廉さこそ何より尊ぶべきだ。
四月一日、日光の御山(男体山の二荒山神社)に詣でる。その昔はこの御山を「二荒山」と称したのを、弘法大師空海がここに寺を開いた際に「日光」と改められた。大師は千年先ともなるこの未来を予見されたのだろうか。今当に、東照大権現の威光は天下を照らし、恩恵は国の隅々に行き渡り、士農工商の民は穏やかに暮らしている。これ以上は憚りも多く、ここで筆を留め置いた。
あらとうと青葉若葉の日の光
(ああ思えば何と尊いことだ。青葉・若葉の全てを、日の光が隈無く照らして輝かせているではないか)
〈黒髪山(日光市男体山)〉には霞が懸かり、雪が未だ白く残る。
剃すててくろかみ山に更衣 曽良
(髪を剃り墨染衣をまとい出家の身となって旅立ったが、今また黒髪山で衣替えの時を向かえ、この先へ思いが改まる)
曽良は、姓は河合で名は惣五郎といった。深川芭蕉庵の近くに住んで、私の日常家事の煩いを助けてくれた。今回、松島や象潟の眺望を共にできると喜び、また旅の辛苦を労りたいと、旅立ちの朝に髪を剃り、墨染衣に身なりを替えて、惣五の名も僧侶風に宗悟と改めた。これによって「くろかみ山」の句ができたので「更衣」の二文字に旅の決意への重みが感じられる。
二十丁(二キロ)ほど山を登ると滝がある。窪んだ岩壁の天辺から流れ出て百尺(三十メートル)岩だらけの真っ青な滝壺に落ち入る。岩窟に身を屈めて入り、滝を裏側から見られるので「裏見の滝」と呼び習わしているのだ。
しばらくは滝にこもるや夏の初
(少しの間、滝裏の岩屋に入っていると、夏籠もりの修行を始めたかのような、爽やかで穏やかな心持ちになるよ)
那須の黒羽(大田原市)という所に知り合いがいるので、これから〈那須野〉の原野を横切って近道しようとする。遙か向こうに見える村を目指して行くと、雨が降り出し日も暮れた。農家に一晩宿を借りて、翌朝また野原の中を進む。そこに野に連れ出された馬がいた。草を刈る男に困っている次第を伝えると、田舎者ではあるがさすがに人情を知らない訳でもなく「どうしたもんかね。だけどこの野原は道があちこちに分かれて、初めて旅する人は道を間違う恐れがあるんで、乗ったこの馬が止まった所で馬を返してくださいな」と貸してくれた。子どもたちが二人、馬の後を追って走ってくる。一人は女の子で、名を「かさね」という。珍しい名前の優しい響きに
かさねとは八重なでしこの名なるべし 曽良
(「かさね」とは、可憐な八重撫子の花を想い浮かべて付けた名前に違いない。可愛い彼女にピッタリだ)
やがて人里に到ったので、御礼のお金を鞍の半ばに結わえ付けて、馬を返した。
【那須野】の場面。左方に農夫から借りた馬に乗って野原を渡っていく芭蕉。馬の足取りは軽快に、馬上の芭蕉も御満悦の表情だ。一方、後ろの曽良は独り荷物を多く担がされ、重たくて難儀な様子。右方では小さな子どもたちが愛らしい。男の子が右手に持つのは馬の鞭か、芭蕉の方に差し上げて追い掛けていることを示す。男の子が女の子の手をシッカリと引いて頼もしい。「かさね」のライラック色の着物が風に靡いて、何とも可憐。
黒羽藩の城代家老、浄坊寺氏(浄法寺高勝、桃雪)の館を訪れる。主人は思いがけない再会を喜び、昼も夜も様々に語り合い、その弟の桃翠(豊明、※翠桃)も朝に夕に通い来て、また自分の家に連れて行ったり、親戚の家にも招かれたりして、何日かを過ごすままに、ある日のこと周辺に足を伸ばして「犬追物」が行われた場所を見物し、歌枕の〈那須の篠原〉に分け入り「玉藻前」の塚(大田原市、狐塚之址碑)を訪ねる。それから八幡宮(那須神社)に詣でた。「那須与市が扇の的を射た時に『取り分け我が郷、那須の氏神正八幡神よ』と祈ったのもこの神社です」と聞くと、霊験が一層確かに感じられた。日が暮れたので、桃翠の家に帰った。
修験光明寺(廃寺)という寺がある。そこに招かれ、開祖の役小角を祀る行者堂を拝観する。
夏山に足駄を拝む首途かな
(新緑の山中で、役行者の一本歯の高下駄を拝んで元気が湧いたから、これを遠く旅立つ新たな門出としよう)
下野国の雲岸寺(大田原市、※雲巌寺)の奥まった所に、私の禅の師匠、仏頂和尚が山中で修行した地がある。
竪横の五尺にたらぬ草の庵 むすぶもくやし雨なかりせば
(一・五メートル四方に満たない小さな庵に、居らなければならないのは不自由なことだ。雨さえ降らなければ)
と「松明の炭で岩に書き付けました」と、いつか話しておられた。「その跡を見てみよう」と、杖を手に雲岸寺に向かうと、土地の人々も互いに誘い合い、若者が多く道中も賑やかに騒いで、思ったより早く寺の下に着いた。山内は奥深い様子で、谷沿いの参道は遥かに続いて、松や杉の林は苔生して湿り、四月というのにひんやりしている。境内の景物を見尽くし、橋を渡って山門を潜る。
「さあ修行された場所はどの辺だろうか」と、裏山によじ登ってみると、岩上に小さな庵が岩窟に寄せて造ってある。中国の高峰原妙禅師の「死関」や法雲法師の石室の様子を目の当たりにするようだ。
木つつきも庵はやぶらず夏木立
(キツツキにも敬う思いがあるのか、この庵を突き壊すことなく守ってくれて、夏の木陰の安らかさは往時のままだ)
と、その場で詠んだ一句を柱に残しておいた。
黒羽から殺生石(那須町)へ向かう。城代家老が馬を出して送ってくれた。馬を引く男が「一句短冊に書いておくれ」と乞う。風雅なことを望まれるものだ、と
野を横に馬ひきむけよほととぎす
(野原の横手へ馬を引き向けておくれ。ホトトギスがしきりに鳴いて呼んでいるみたいだから、そちらへ行ってみよう)
殺生石は温泉が湧き出る山懐にある。石が放つ毒気は未だに衰えず、蜂や蝶などが地面を覆い尽くすほど重なり合って死んでいる。
また西行が「道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」と詠んだ柳は、芦野の里(那須町)にあって田圃の畦道に残っている。ここの領主である戸部氏(芦野資俊、桃酔)が「この柳を一度はご覧に入れたい」と、折りにつけていっておられたことから、どんな所だろうと思っていたが、今日やっとこの柳陰に立ち寄ることができた。
田一枚植て立去柳哉
(西行はしばし立ち止まったというが、私は田圃一枚に苗を植え終わるのを見届けて、ゆっくり立ち去りますよ柳陰を)
頼りない思いで旅の日々を重ねてきたが〈白河の関(福島県白河市)〉にやって来て旅への心持ちが定まった。(平兼盛が)「便りあらばいかで都へ告げやらん今日白河の関は越えぬと」と、伝えたく思ったのも尤もだ。特にこの白河の関は東国三関の一つとして、風雅を好む人は心に留めている。(能因法師の「都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関」で)秋風の音を耳にし(平親宗の「もみじ葉の皆くれないに散しけば名のみ成けり白河の関」で)紅葉を想い浮かべると、目の前の青葉の梢も一層趣き深いことだ。(藤原季通の「見て過ぐる人しなければ卯の花の咲ける垣根や白河の関」の)卯の花の白さに、野茨の花も咲き添って(久我通光の「白河の関の秋とは聞きしかど初雪分くる山の辺の道」の)雪道を越えて行く思いがする。「昔の人は(この関を越えるのに、能因の歌を敬って)冠を正し衣服を改めた」などと、藤原清輔も書き置かれたそうだ。
うの花をかざしに関のはれ着哉 曽良
(改めるほどの衣装も無いけれど、せめて白い卯の花を簪に挿して、この白河の関を越える晴れ着としよう)
こうして白河の関を越えて行くほどに、阿武隈川を渡る。左手に会津磐梯山が高く聳え、右手には岩城・相馬・三春などの郷が広がり、背後には常陸(茨城県)や下野(栃木県)との境に山々が連なる。影沼という所を通り過ぎると、今日は空が曇って何の物影も映らなかった。
須賀川の宿場(須賀川市)で等窮(等躬)という者を訪ねると、四・五日引き留められた。先ずは等窮が「白河の関はどんな印象でしたか」と尋ねるので「長旅に苦しみ身心疲れているところに、見事な風景に心を奪われ、昔の人が詠んだ古歌の情趣が一段と身にしみて、十分に想いを巡らせませんでした。
風流のはじめやおくの田植うた
(これこそ庶民の風流の原点だ。この陸奥国に入って初めて耳にした、田植え歌の鄙びた味わいよ)
何も無しに関を越えるのもさすがにどうかと」と言い訳すると、これを発句に脇句・第三句と続けてくれて、三巻の連句を成した。
この宿の傍らに、大きな栗の木の下に身を寄せて、俗世を避けて暮らす僧侶がいる。「(西行が)『山深み岩に下垂る水溜めんかつがつ落つる橡拾う程』という深山もこんなだろうか」と静寂さに感じ入って、手許に書き付けた言葉は
「『栗』の字は『西』の『木』と書くので、西方浄土に縁があるとして、行基菩薩は生涯で杖にも柱にも栗の木を用いられた」という
世の人の見付ぬ花や軒の栗
(世間の人が目に留めない栗の花みたいな床しさだ。栗の木陰の軒下で静かに西方浄土への縁を願うあなたは)
【須賀川】の場面。葉の茂った大きな栗の木を表し、右手へ伸ばした枝の下に茅屋を描いて、家内に墨衣の人物を配する。本来家屋の周囲を取り囲むはずの間垣の外に庵が出張っていて、中に居る人はまるで見世棚の店主のようだ。芭蕉がこの人の静かな暮らしぶりを「世の人の見付ぬ花」と注視した意を、蕪村も解って活かそうとした。景観よりも人事に主眼を置いて、その人の姿を明瞭に表すことにしたのである。
等窮の家を発って五里(二十キロ)ぐらい、桧皮の宿場(福島県郡山市)より少し離れた所に〈安積山〉がある。街道からほど近い。この付近には沼が多い。(藤原実方が端午の節句で菖蒲の代わりにしたという)「花かつみ」を刈る頃もそろそろ近いかと「どの草のことを『花かつみ』というのですか」と人々に尋ねてみたが、全く知る人がいない。安積沼を訪れ、地元の人に聞いて「かつみ、かつみ」と尋ね歩いたが、日が山に沈み始めてしまった。二本松(二本松市)から街道を右手に折れて(謡曲『安達原』の鬼婆が住んだという)黒塚の岩屋を一見し、福島(福島市)で宿を取る。
明くる日は(源融の「陸奥のしのぶもぢずり誰ゆえに乱れんと思ふ我ならなくに」で知られる)信夫捩󠄁摺の石を訪ねようと〈信夫〉の里(福島市)に行く。かなり離れた山間の里に、捩󠄁摺石は半ば土に埋もれてあった。村の子どもたちがやって来て教えてくれて「以前はこの山の上にあったんだけど、行き来する人たちが麦畑を踏み荒らしてこの石で摺りを試されるのが嫌で、この谷に突き落としたら、石の表側が下向きに倒れてしまったんだ」という。確かにありそうなことだ。
早苗とる手もとや昔しのぶ摺
(早乙女たちが早苗を手に取る昔ながらの仕種に、かつての信夫捩摺の布染めの手つきが偲ばれるようだ)
月の輪の渡し(福島市)を越えて、瀬の上という宿場(瀬上町)に出た。(源義経の家臣、佐藤継信・忠信兄弟の父で)この地の荘官だった佐藤元治の旧居跡は、左手の山間へ一里半(六キロ)ほどにある、飯塚の里、鯖野という所と聞いて、尋ねながら行くと、丸山という地に尋ね当たった。「ここが荘官の館跡です。麓にも大手門の跡があります」などと土地の人が教えてくれるそばから涙を流し、また近くの古寺(福島市、医王寺)には佐藤一族の墓碑が遺る。取り分け(戦死した継信・忠信の甲冑武具を着て、兄弟の母を慰めたという)二人の嫁の像が一番哀れである。「女性ながら健気な行いで、名を後世に遺したものだなあ」と袂で涙を拭った。(故人の徳を慕う)「堕涙の石碑」は、遠く中国にあるばかりではない。寺に上がって茶をいただくと、ここには源義経の太刀と弁慶の笈とが遺され宝物とされる。
笈も太刀も皐月にかざれ帋幟
(弁慶の笈も義経の太刀も、端午の節句に飾る紙幟とともに披露して、武勇の誉れを示すがよい)
【飯塚の里】の場面。芭蕉がいう「二人の嫁がしるし」として描かれるのは、実は宮城県白石市の甲冑堂に祀られた二像である。兄弟の妻二人が、亡き夫の甲冑を各々身に着け、兄弟の母を慰めた姿。海の見える杜美術館所蔵の「奥の細道画巻」では、同図に「各鎧を着し一人は釼を按じ一人は弓箭を取る」と注記され、蕪村は木像の姿を知っていたと判る。本図で二人の鎧は緋縅と黒糸威とに着分けられ、持つ物も剣と長刀とになる。
当に五月一日のことだった。
その夜は飯塚(福島市飯坂温泉)に泊まる。温泉があるので湯に入ってから宿を借りると、土間に莚を敷いた侘びしい粗末な家だった。灯火も無いので、囲炉裏の火の近くに寝床を作って横になった。夜中になると、雷が鳴り雨も酷く降って、寝ている上から雨漏りし、蚤や蚊に刺されて眠れず、持病さえ起こって人心地を無くすようだった。夏の短夜で空もやがて明けたので、また旅立った。
けれども昨夜の重苦しさのまま、気分が優れない。馬を借りて桑折の宿場(桑折町)に出た。「これから長い道程があるのに、こんな病に煩わされては心配だ」と思ったが「辺境を旅行くからにはこの身は捨てたと覚悟し、道中に命を落としたとしても天の命ずるところだ」と、気力を多少は持ち直し、思いのままに道を踏みしめて、伊達藩の大城戸(国見町)を越えた。
鐙摺の細道や白石の城下(宮城県白石市)を過ぎて、笠島の郡(名取市)に入ったので「藤原実方の墓はどの辺りでしょう」と土地の人に尋ねると「ここから遠く右手に見える山間の里を箕輪・笠島といいます。そこに実方所縁の道祖神の神社や、西行が詠んだ形見の薄などが今もあります」と教えてくれた。数日の五月雨で道がとても悪く、身体も疲れていたので、遠くから眺めるだけで通り過ぎたが、簑輪も笠島も五月雨に縁がある地名と思い
かさしまはいずこさつきのぬかり道
(藤原実方所縁の笠島はどんなところだったのだろう。五月雨に泥濘んだ道のせいで訪れることが叶わなかったよ)
岩沼(岩沼市)に宿を取る。
〈武隈の松(二木の松)〉には本当に目が覚める思いがした。幹が根元から二股に分かれて、昔の人が歌に詠んだ姿を失っていないと知った。直ぐに能因の逸話を想い起こした。その昔、陸奥守として下った方が、この木を伐って名取川の橋杭にされたことなどがあったからか、能因は「武隈の松はこのたび跡も無し千歳を経てや我は来つらん」と詠んだ。その時々に、ある者は伐り、ある者は植え継ぐなどしたとは聞くが、今また千年前から続く形を整えて、何と目出度い松の姿であることだ。
たけくまの松見せ申せ遅ざくら
(武隈の松を見せて差し上げてくれ、陸奥の遅桜よ。まだ咲いていたなら、その花とともに愛でられよう)
の句を(草壁)挙白という門人が䬻別にくれたので
さくらより松は二木を三月越
(桜の弥生に旅立ってより待ち望んでいた、二木の松の姿を、三ヶ月を越えて遂に見ることが叶ったよ)
名取川を渡って仙台(仙台市)に入る。家々で軒に菖蒲を葺く五月四日(端午節句前日)だ。宿屋を定めて四五日滞在した。この地に絵描きの加右衛門という人がいる。なかなか風雅を愛する人物と耳にして、知り合いになった。この人が「日頃から、定かでない歌枕の場所を調べてありますので」といって、ある一日案内してくれた。〈宮城野〉は萩が茂り合って、秋の景色が想い浮かべられる。〈玉田・横野・榴ヶ岡〉は(源俊頼が「とりつなげ玉田横野の放れ駒つつじが岡にあせみ咲くなり」と詠んだ)馬酔木の咲く頃だった。木漏れ日も差さない松林に入ると「ここが〈木の下〉という所です」という。昔もこのように露深かったので、古歌でも「みさぶらい御笠と申せ宮城野の木の下露は雨にまされり」と(笠を勧めるよう)詠んだのだろう。薬師堂や天神の御社(榴岡天満宮)などを参拝して、その日は暮れた。
その後もなお加右衛門は、松島や塩竃の所々を絵に描いて贈ってくれた。そして、紺染めの鼻緒を付けた草鞋二足を餞別にくれた。なるほどこの通り、風流の達人は、別れに至ってこそその実を現すものだ。
あやめ艸足に結ん草鞋の緒
(まるで菖蒲の花を足に結わえ付けたようだ。餞別の草鞋の紺色の鼻緒に元気をもらって、これからの旅も安心だ)
加右衛門の絵図を頼りに進んで行くと、奥の細道の山際(利府町)に(藤原仲実の「みちのくの十符の菅薦七符には君を寝させて三符に我が寝む」で知られる)「十符」の菅があった。今も毎年「十符の菅薦」を作って藩主に献上するそうだ。
壺碑(多賀城碑) 市川村多賀城(多賀城市)にある。
壺の碑は、高さは六尺余(約一八〇センチ)横幅は三尺(九〇センチ)ぐらいか。覆われた苔を彫り込んだかのように、文字は不鮮明だ。ここから四方の国境までの距離を記している。「この城(多賀城)は、神亀元年(七二四)按察使で鎮守府将軍の大野東人が築いた所である。天平宝字六年(七六二)参議で東海・東山道節度使で同じく将軍の恵美(藤原)朝獦が修理をした。十二月一日」と見える。神亀元年は聖武天皇が即位された年に当たる。
古より詠み継いだ歌枕が数多く語り伝えられるというが、山は崩れ川は流れを変え道は新たになり、石は地に埋もれて土に隠れ、木は枯れて若木に替えられるなど、時は移り世は変わってその有り様が確かでないものばかりだが、この地に至って疑い無く千年変わらぬ姿に、当に目の前に古人の心を見た思いだ。これこそ巡歴で得られた恩恵、生きている者の悦びで、旅の苦労も忘れて涙が溢れるばかりである。
【多賀城碑】
石は高さが六尺五分、幅が三尺四寸
多賀城は 京を去ること千五百里
蝦夷国との境を去ること一二〇里
常陸国との境を去ること四一二里
下野国との境を去ること二七四里
靺鞨国との境を去ること三千里
西 この城(多賀城)は神亀元年(甲子)按察使で鎭守将
軍を兼ねる従四位上勳四等の大野東人が築いた。
天平宝字六年(壬寅)参議・東海東山節度使であり、
従四位上の仁部省卿で按察使・鎮守
将軍を兼ねる恵美朝獦が修理した。
天平宝字六年十二月一日
『日本総国風土記』に曰く「陸奥国宮城郡の坪碑は鴻之池にある。旧鎮守府の門碑のために、恵美朝獦がこれを建て、見雲真人が清書した。異域から本邦への行程を記し、旅人が道に迷わないようにした」
陸奥のいはでしのぶはえぞ知らぬ書きつくしてよ壺の碑 右大将 源頼朝
陸奥は奥ゆかしくぞ思ほゆる壺の碑外の浜風 西行
多賀城の事は『続日本記』の聖武皇帝天平九年夏四月の記事に初めて見える
神亀元年(甲子)は聖武帝の元年で安永八年巳亥までは一〇七五年
天平宝字六年(壬寅)は廃帝(淳仁天皇)の四年で安永八年巳亥まで一〇三七年
それから、歌枕に知られる〈野田の玉川〉や〈沖の石〉を訪ねた。〈末の松山〉には寺が造られて「末松山」と称す。松林の合間は皆墓地となり「羽根を交わし枝を連ねる(比翼連理)と誓った仲でも、果てにはこの無常な有り様か」と悲しみに耽り〈塩竃の浦〉に出て夕暮れの鐘の音に耳を傾けた。梅雨空が少しだけ晴れ、夕月の光が柔らかく照らして〈籬が島〉も間近く見える。漁師の小舟が次々に帰り来て、魚を分け合う声を聞くと「陸奥はいづくはあれど塩竈の浦漕ぐ舟の綱手かなしも」と詠んだ古人の心が想われて、何とも哀れである。
その夜、盲目の法師が琵琶を弾きながら「奥浄瑠璃」というものを語る。平家琵琶でも幸若舞でもない。鄙びた調子で声を張り上げて、寝ている枕近くに聞こえて喧しかったが、確かに辺境でも昔ながらの風俗を守っていることを感心に思った。
朝早く、塩竃の明神(塩竈市、鹽竈神社)に詣でる。藩主(伊達家代々)が再興されて、社殿は柱も立派で彩られた垂木は華やかに、石段が高くまで続いて、朝陽が朱の玉垣を輝かしている。このように遠く離れた辺地にまで、神々が霊験灼かに在すことこそ、我が国の美風であり、とても貴いことだ。神殿の前に古い宝灯がある。金属の扉の表に「文治三年(一一八七)和泉三郎(藤原忠衡)が寄進した」とある。五百年前のその人の姿が今目の前に浮かんで、思わず感激した。彼は勇気・正義、忠孝・礼節を備えた武士だった。その名は今に伝わり、慕わない者はいない。当に「人は正しく道を勤め、義を守るのがよい。名声もまた自ずとその行いに伴う」という通り。
時刻はもう正午に近い。船を借りて松島に渡る。その間の距離は
【塩竃】にて琵琶法師が「奧浄瑠璃」を語る場面。右方で琵琶を弾きつつ演じる法師は、調子が出て来たのか前方に身を乗り出し、大きく開いた口から音声を発する。左方には宿の相客か、男女三人を聴衆とする。目を閉じて微笑みながら聴き入る婦人に対し、頬に手を当てる口ひげの老人は、顔を顰めてむしろ不興そうな様子。芭蕉の「枕ちかうかしましけれど」という直截な表現に応じ、蕪村が表した人物像か。
二里(八キロ)ほど、雄島の磯に着いた。
さて既に言い古されたことだが、松島は日本第一の景勝地であって、全く中国の洞庭湖や西湖にも劣らない。東南から海が入り込んで、入り江の長さは三里(十二キロ)、中国の銭塘江のように潮が満ちる。様々な島を集め尽くして、聳え立つものは天を指差し、伏すものは海面に腹這う。あるものは二重に重なり、三重に畳まれて、背負うものあり、抱きかかえるものあり、子や孫を愛おしむかの如くだ。松の緑は色濃く、枝葉は潮風に吹き撓められて、曲がり具合は自然と形を整えたようだ。その雰囲気はうっとりとするようで(蘇東坡が西湖と美女の西施とを比べたように)美人が顔を化粧する様だ。千早振る神代の昔に、大山祇の神が為した業なのだ。天地の創造者の仕事に対し、誰が文筆を振るい、言葉を尽くせるというのか。
雄島の磯は陸からの地続きで、海に突き出た島だ。(瑞巌寺を中興した)雲居(希膺)禅師の禅堂跡や座禅石などがある。また、松の木陰に浮き世を離れて住む人も稀に居られて、落葉や松笠などを焚いて煙を上げる草庵で長閑に暮らし、どのような人物かは知らないまま、何より心惹かれて立ち寄っていると、月が海に映って、昼の眺めとはまた趣きがあらたまった。
入り江近くに帰って宿を探すと、ある家で窓を開け広げた二階に寝床を作ってくれた。風や雲の中に旅寝しているようで、不思議と神妙な気分になった。
松しまや鶴に身をかれほとゝぎす 曽良
(絶景の松島なのだから、優雅な鶴の姿を借りて鳴き渡ったらどうかね、ホトトギスよ)
私は言葉が出ないまま、眠ろうとしても眠れない。深川の草庵で別れた際、友人の(山口)素堂は「松島の詩」を持ち、原安適は「松かうらしま」の和歌を贈ってくれた。荷物袋を開いて、今宵の楽しみの縁とする。また、門弟の杉風や(中川)濁子の発句もある。
五月十一日、瑞岩寺(松島町、瑞巌寺)に詣でる。この寺は昔、三十二世となる真壁平四郎(法身性西)が出家して唐(※宋)に留学し、帰朝した後に開山した。その後、雲居禅師の教えが慕われて、七堂伽藍も改築され、金箔の壁が荘厳に光り輝く、仏の世界さながらの大寺院となったのだ。「彼の見仏上人の寺は何処なのだろう」と偲ばれる。
五月十二日、平泉を目指し、歌枕の〈姉歯の松〉や〈緒絶の橋(大崎市)〉などがあると伝え聞いて、人通りも稀な、雉・兎や狩人・樵夫が通うような道を、どこであるかもよく分からないまま、終に道を間違えて石巻(石巻市)という港に出た。(大友家持が)「天皇の御代栄えんと東なる陸奥山に金花咲く」と詠んで称えた金華山を海上に見渡し、数百隻の廻船が入り江に集まり、家々は軒を連ね、炊事する竈の煙がたくさん立ち上っている。「思い掛けずこのような所に来てしまったなあ」と、宿を借りようとするが、一向に宿を貸す人がいない。漸く粗末な小家に一夜を明かして、翌朝また知らない道を迷い行く。〈袖の渡り〉〈尾駮の牧〉〈真野の萱原〉など、歌枕の地も見ずに過ぎ、北上川の長い土手を行く。心細い思いで長沼に沿って、戸伊摩(登米市)という所に一泊して、平泉(岩手県平泉町)に到着した。その間の距離は二十余里(八十キロ)ぐらいと思えた。
奥州藤原氏三代の栄華も、邯鄲一炊の夢の内の出来事のように消え去り、南大門の跡は一里(四キロ)ほど手前にある。秀衡の館跡(伽羅御所)は田や野原となって、金雞山だけが往時の姿を留める。
先ず、義経が陣取った高館(衣川館)に登ると、北上川は南部地方から流れてくる大河だ。衣川は、和泉三郎の城(泉ケ城)を巡って、高館の下で北上川に流れ入る。泰衡たちの居館跡(柳之御所遺跡)は、衣が関(衣河関)を隔てとして、南部からの入口を守り固め、蝦夷を防いだと見られる。
将に忠義な臣下たちを選んでこの高館に立て籠もり、功名を成したがそれも一時のこと、今は草むらとなっている。(杜甫がいう)「国破れて山河あり、城春にして草木深し」の通りだと、旅笠を敷いて腰を下ろし、時が過ぎるのを忘れて悲しみに暮れたのだ。
夏艸や兵どもが夢のあと
(今は夏草が生い茂るばかりだが、かつては藤原三代や義経・弁慶たち、兵共が各々夢を想い描いた地だったものを)
うの花に兼房みゆる白毛かな 曽良
(卯の花の白さに、義経の最期に奮戦した十郎権頭兼房の姿が偲ばれるのは、その白髪頭の所為だろうか)
以前より伝え聞いて感心していた(中尊寺の金色堂・経蔵)二堂の扉を開けてくれた。経堂(経蔵)には藤原氏三代の像(※文殊五尊像)を遺し、光堂(金色堂)には三代の棺を納め、阿弥陀三尊の仏像を安置する。宝飾は散り失せ、美麗な扉は風で傷み、金色の柱は風雪に朽ちて、既に廃墟の草むらと成るべきを、堂の四面を新たに囲み瓦屋根で覆って雨風を防ぎ、当面は千年の姿を留める記念物となった。
さみだれのふりのこしてや光堂
(毎年毎年五月雨は降るというのに、ここだけは尊んで除けて残してくれたのか、見事に光り輝いている金色堂だ)
【平泉】で描くのは「笠打敷て時のうつるまで泪を落し侍りぬ」の場面。芭蕉の文が高館からの眺望を雄大に表すのに対し、蕪村はそうした風景を一切描かない。芭蕉と曽良とが坐り込む姿は、単に道中で一休みしているかのよう。しかし蕪村は周囲の景観を全て省き去ることで、悲しみに暮れる芭蕉の心情にクローズアップしているのだ。芭蕉は目を細め口を閉ざし、傾けた体を杖に寄せる。曽良は片手で目頭を押さえている。この感極まった場面で上巻を終える。
奥の細道画巻 第一巻 俳句索引
【あ】
あやめ艸足に結ん草鞋の緒
あらとうと青葉若葉の日の光
うの花に兼房みゆる白毛かな 曽良
うの花をかざしに関のはれ着哉 曽良
笈も太刀も皐月にかざれ帋幟
【か】
かさしまはいずこさつきのぬかり道
かさねとは八重なでしこの名なるべし 曽良
草の戸も住替る代や雛の家
木つつきも庵はやぶらず夏木立
【さ】
さくらより松は二木を三月越
早苗とる手もとや昔しのぶ摺
さみだれのふりのこしてや光堂
しばらくは滝にこもるや夏の初
剃すててくろかみ山に更衣曽良
【た】
田一枚植て立去柳哉
たけくまの松見せ申せ遅ざくら
【な】
夏艸や兵どもが夢のあと
夏山に足駄を拝む首途かな
野を横に馬ひきむけよほととぎす
【は】
風流のはじめやおくの田植うた
【ま】
松しまや鶴に身をかれほとゝぎす 曽良
【や】
行春や鳥啼魚の目は泪
世の人の見付ぬ花や軒の栗