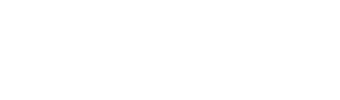奥の細道画巻 第二巻
[2-1]
南部地方へと続く道を遠くに眺めて、岩手山の里(宮城県大崎市)に泊る。〈小黒崎〉〈美豆の小島〉の歌枕の地を過ぎて、鳴子温泉から尿前の関を通って、出羽の国(山形県)に越えようとする。この道筋は旅人も稀なところなので、関所の役人に怪しまれて、漸くのことで関を越えた。
【尿前の関】にて、旅人稀なる道を行く芭蕉たちが怪しまれる。取り調べの関守は、まるで見得を切るようなポーズ。前に乗り出した姿勢は、役人の居丈高な様を表したもの。これに対して、芭蕉たちは低姿勢の様子。曽良が芭蕉を庇って前に出て、役人に深々と頭を下げる。全体、芝居の一場面の如く、台詞の遣り取りが聞こえてきそうなシーンだ。本文三行ほどの記事だが、蕪村はどのような意図からこの場面を選んだのか。
大きな山を登ると、日がもう暮れたので、国境を守る人の家を見つけて宿を求めた。三日の間、雨風が荒れて、縁の無い山の中に逗留する。
のみしらみ馬の尿するまくらもと
(蚤や虱が集るし、馬の小便する音が寝ている枕元に聞こえる。まあこんな経験も旅の一興さ)
家の主がいうには「ここから出羽の国へは大きな山に阻まれて道も不確かなので、道案内の人を頼んで越えるのがよいでしょう」とのこと。それならばと思い、人を頼んでみると、屈強な若者が、反った脇差を腰に横たえ、樫の杖を携えて、我々の先に立って行く。「今日こそは必ず、危ない目に遭うに違いない日だぞ」と、不安な思いをしながら後に付いて行く。先に主がいった通り、高い山は静まりかえって鳥の声一つ聞かない。繁った木々の下は暗がりとなって夜道を行くようだ。(杜甫が喩えた)「雲端に土ふる(霾雲端)」ような覚束ない心持ちで、小笹の中を踏み分け踏み分け、沢を跨ぎ岩に躓き、肌には冷や汗を流して、最上の庄(山形県)に出た。この案内した男がいうには「この道では必ず思わぬ事件や事故があります。無事に送って差し上げられて、幸いでした」と喜んで別れた。後から聞くにも胸がどきどきするばかりだ。
尾花沢(尾花沢市)に入り(鈴木)清風という人物を訪ねた。彼は金持ではあるが、人柄には品格がある。京都にも時々通って充分旅の情を心得ているので、数日引き留められて、長旅の労りにと様々に持て成してくれた。
涼しさを我宿にしてねまるなり
(「清風」の名の通り、この宿の涼しさは実に心地好い。まるで自分の家に居るかのように寛いで休んでいるよ)
【山刀伐峠】越えの場面では、険しい山道を進んでいく心細さを表すかのように、芭蕉と曽良とがくっつき合って歩を進めている。腰が引けがちな芭蕉を、曽良が後ろから手を差し入れて脇を支える。一方、先導する若者は、鮮やかな色の縞の着物を尻からげ、太股も露わに威勢が良い。右肩を脱いで杖を持つ腕の筋肉の盛り上がりを見せ、若々しさが強調される。手足を大きく広げた活発で逞しい様子は、芭蕉たちと好対照である。
這出よかひやか下のひきの声
(這い出てきて姿を見せておくれ、蚕小屋の下で鳴く蟇蛙。その声は私を呼んでいるのかい)
まゆはきをおもかげにして紅の花
(眉刷毛に似たその形から連想されて、化粧をする女性の姿が眼に浮かんでくるよ。艶やかなベニバナの花は)
蚕飼する人は古代のすがたかな 曽良
(蚕を飼う人たちは、古から続く素朴な仕事をそのままに、大切に守り伝えている姿が尊いことだ)
「山形藩の領内に立石寺(山形市)という山寺があります。慈覚大師(円仁)の開基で、取り分け清らかで静かな所です。是非一見されるのが良いでしょう」と人々が勧めるのに従って、尾花沢から引き返し、その間の距離は七里(約三十キロ)ほどだった。日はまだ暮れていないので、麓の僧房に宿を借りておき、山上の本堂へと登った。岩の上に巌を重ねたような山で、松や柏の木は年経て、岩肌は古びて苔が滑らかに覆い、岩上に建つ御堂はどれも扉を閉じて物音一つ聞こえない。崖の縁を廻り岩々を伝い歩いて仏堂を参拝すると、絶景は静まり返って、心が澄み渡っていく様のみが感じられる。
しづかさや岩にしみ入蝉の声
(これこそが静寂というものだ。岩岩の間に染み込んでいって消え去ってしまうよ、響き渡っている蝉の声さえも)
最上川を舟に乗って下ろうとして、大石田(大石田町)という所で天気が良くなるのを待つ。「この地にかつて俳諧の教えが伝わってから、忘れられぬ華やかな古風を懐かしむ一方、葦笛・胡角の一声のような新味にも心惹かれて、俳諧の道を手探りしつつも、新古二つの流儀に迷っておりましたが、指導してくださる方がおられなかったので」と乞われて、意を尽くせぬまま連句一巻を残した。今回の趣向はこんな次第ともなった。
最上川は、陸奥から流れ出て山形が上流となる。碁点・隼などという恐ろしい難所がある。歌枕の地〈板敷山〉の北を流れて、最後は酒田の海に流れ入る。両岸から山が覆い被さり、茂みの中を舟で下る。この舟に稲を積んだものを(古歌の)「稲舟」というのだろう。白糸の滝は青葉の合間に流れ落ち(義経の家臣、常陸坊海尊を祀る)仙人堂は岸に臨んで建つ。川の水は漲って、舟は危なかった。
さみだれをあつめてはやし最上河
(五月雨に降った雨水を集めに集めて、こんなにも速い流れにしてしまったよ。全くこの上ない川だな最上川は)
六月三日、羽黒山に登る。図司左吉という人を訪ね、その執り成しで(山中の統括者である)別当代の会覚阿闍利にお目にかかる。南谷の別院に泊めてくださり、情け深く心濃やかに持て成してくださった。
有がたや雪をかほらす南谷
(有難いことです。羽黒山の残雪の涼しさが風に薫る、この南谷別院を宿にしてくださった阿闍梨様)
六月五日、羽黒権現に詣でる。この山を開いた能除大師(蜂子皇子)はいつの世の人なのかを知らない。『延喜式』には「羽州里山の神社」と記される。書き写す際に「黒」の字を「里山」と誤ったのか。「羽州黒山」を省略して「羽黒山」といったのか。「出羽」といったのも「鳥の羽毛をこの国の産物として献上した」と『風土記』にあるからとかいう。月山や湯殿山を合わせて「出羽三山」とする。この寺は、江戸の東叡山(寛永寺)に属して、天台(大師智顗の)「止観」の教えを月の如く明らかに「円頓融通」を宗とする仏法の灯を掲げ続けて、僧侶の宿舎は棟を並べ、修験者は修行に励んで、霊山霊地として効験あることを、人々は尊び、そしてまた畏れている。繁栄は永く続いて、貴い御山というべきだ。
六月八日、月山に登る。木綿注連(と呼ぶ袈裟)を身に着け、宝冠(と称する白布)を頭に巻き、強力という者に先導されて、霧立ち籠める山道を、氷や雪を踏み締めながら登ること八里(三十二キロ)。さらに「太陽や月が行き来する雲中の関所に入ったのか」と怪しく思うほどに、息は絶え体も凍えて頂上に到ると、日は沈んで月が現れた。笹を布き篠を枕にして、横になって夜が明けるのを待つ。朝陽が出て雲が消えたので、湯殿山へと下った。
谷の傍らに鍛冶小屋というものがある。この国の刀鍛冶は、霊水を選んで、この地で精進潔斎して剣を打つ。最後に「月山」と銘を刻んで、人々に賞賛されるものとなる。中国の昔、龍泉の水で剣を焼き入れしたという、干将・莫耶の夫婦の故事が想い起こされ、一つの道を究める信念の深さが知られた。
岩に腰掛けて少し休んでいると、三尺(九〇センチ)ほどの桜で、蕾が半ば開いているものがある。降り積んだ雪の下に埋もれていても、春を忘れぬ遅桜の花の心は不思議なものだ。(空想のものである)「炎天の梅花」が目の前で薫るかのようだ。行尊の歌の情趣も今思い出されて、一層優れて感じられる。総じてこの山中での委細は、行者の心得として、他言することを禁じている。よってこれ以上は筆を止めて記さない。
宿坊に帰り、阿闍梨の求めに応じて三山巡礼に因む句を短冊に書いた。
すゞしさやほの三か月の羽黒山
(涼しいものだ。仄かな三日月が空にかかる羽黒山の夕暮れに、ちょうど心地よい風が吹いてくれるよ)
雲の峰いくつ崩て月のやま
(昼に湧き起こった白雲の峰が、幾つも崩れて、夜には月に照らされる、残雪の白い月山となったのか)
語れぬ湯どのにぬらす袂かな
(この山の禁忌で話すことはできない。湯殿で濡らした袂のことは、涙を落としたその訳さえも)
ゆどの山銭ふむ道の泪かな 曽良
(神聖な湯殿山では、投げられたままの賽銭を踏みつつ参道を進む有り難さに、自然と涙が溢れてくるよ)
羽黒山を発って、鶴岡の城下(鶴岡市)で長山重行という武士の家に迎えられ、俳諧連句の一巻を成した。図司左吉も一緒に見送ってくれた。
川舟に乗って、酒田の港(酒田市)に下る。淵庵不玉という医者のもとに宿る。
あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ
(暑そうな温海岳(鶴岡市)の山から、風吹く吹浦(遊佐町)の海へと、川舟で下りながらの夕涼みは気持ち好い)
暑き日を海にいれたり最上河
(暑かった一日をすっかり海に流し入れてしまったのだね、涼しくなったよ。やっぱり最上川はたいしたもんだ)
海や山、水辺や陸地の景勝の数々を集め尽くした有り様に、今また象潟(秋田県にかほ市)に詩心を悩まされる。酒田の港から東北の方角に、山を越え、磯を伝い、砂浜を歩いて、海際を行くこと十里(四十キロ)。日が少し傾く頃には、潮風は浜の砂を吹き上げ、雨は朦朧と烟って鳥海山を隠す。闇のように何も見えない中では句作も成らず(蘇東坡に倣って)「雨もまた趣きがある」と気取ってみたり「雨の後に晴れた景色が楽しみだ」と思い直したりと、漁師の小屋に入り込んで、雨が晴れるのを待つ。
翌朝、空はよく晴れて、朝陽が美しく輝き出た頃合いに、象潟に舟を浮かべた。先ず、能因島に舟を寄せて、能因が三年間隠棲した跡を訪れ、対岸に舟から上がると「象潟の桜は波に埋もれて花の上漕ぐ海士の釣り舟」と詠んだ桜の老木が、西行の記念として遺されている。入り江の岸に御陵があり、神功皇后の墓だという。寺の名は干満珠寺(蚶満寺)だそうだ。この地に行幸されたとは聞いたことが無い。何か理由があるのだろうか。この寺の方丈に坐って、簾を巻き上げると、風景が一望の内に見渡せて、南には鳥海山が天高く聳え、その影が海面に映って見える。西は有耶無耶の関(宮城県川崎町)が道をさえぎり、東には堤を築いて秋田に通じる道が遥かに続き、北に海が広がって波が入り込むところを汐越と呼ぶ。入り江の広さは一里(四キロ)ほど、その光景は松島に似通うがまた異なり、松島は笑っているかのようで、象潟は憂えているかのようだ。寂しさや悲しさを交えて、この地の情趣には思いを掻き乱すものがある。
象潟や雨に西施がねぶの花
(象潟が雨に烟る情景からは、美女の西施が眠る面差しやら、濡れそぼるネムノキの花やらが、悩ましく想い浮かぶ)
しほこしや鶴はぎぬれて海涼し
(汐越の浅瀬で、餌を漁るツルにも波が打ち寄せて脛まで濡れている。海辺の涼しさを目で見て感じる光景だ)
祭礼
きさがたや料理何くふ神祭 曽良
(この象潟で、料理は何を食べるというのだろう。魚を食べることを禁じている、熊野神社のお祭りの日に)
美濃国の商人
蜑の家や戸板を敷て夕すゞみ 低耳
(漁師の家では、屋外に雨戸の戸板を敷いて、その上で夕涼みをしている。鄙びた暮らしぶりが微笑ましい)
岩上にミサゴの巣を見る
波こえぬ契ありてやみさごの巣 曽良
(その岩の上までは波がやって来ないとでも約束があるのだろうか、ミサゴは平気で巣作りしているよ)
【酒田】に至った記述の辺りに、五人が寄り合う図を添える類作もあるが、本図が見えるのは象潟の後。文机に向かうのは曽良で、筆を執って横紙に何かを記している。何れかの句会の場面を写すものだろう。山形美術館の屏風では人数が三人となり、図の脇に「文月や六日も常の夜には似ず」「荒海や佐渡によこたふ天河」の二句が記され、越後に入ってからのこととなる。蕪村は、どの句会の様子と特に限定していないのではないか。
酒田では名残を惜しんで日数を重ねたが、北陸道に踏み入ろうとその空の雲を眺め、遙かな道程に胸が痛むような思いでいると、加賀の府(石川県金沢市)まで百三十里(五百二十キロ)と教えられた。
鼠ヶ関(山形県鶴岡市)を越えて、越後(新潟県)の地に入れば歩みも新たに、越中(※越後)の国の市振の関(糸魚川市)に到った。この間は九日、暑さや湿気に煩って心身ともに疲れ、持病も起こったので出来事を記していない。
ふみ月や六日も常の夜には似ず
(七月になって、今日は六日。明日は七夕だというので、何だかいつもの夜とは違って人恋しい思いがするよ)
あらうみや佐渡によこたふ天河
(荒れた暗い海に隔てられた佐渡島に向かい、大きな架け橋のように横たわる天の川が静かに輝いている)
今日は、親不知・子不知・犬戻・駒返などという、北国で一番の難所を越えて疲れてしまったので、枕を引き寄せて寝ていると、一部屋隔てた表の方から、若い女の声が二人ほど聞こえる。年老いた男の声も交じって語り合うのを聞くと、越後の国の新潟(新潟市)というところの遊女だった。お伊勢参りをしようとして、この関まで男が送り、明日は故郷へ返す手紙を認めて、些細な言伝などしているのだ。「(古人が「白波の寄する渚に世を過ぐす海人の子なれば宿も定めず」と詠んだように)無常な世間に身を持ち崩し、人の道から愚かにも落ちぶれ、縁の無い出会いを繰り返して日々悪業を重ねる、何とも情けない」と物語るのを、聞きつつも寝入り、朝になって旅立つ折に、我々に向かって「行き方も知らない旅路が心細く、どうにも覚束ずに不安でございますので、見え隠れにもあなた様方の後について参りたく存じます。墨衣の姿でおられるお情けに慈悲のお恵みをいただき、ご縁に縋らせてくださいませ」と涙を流す。可哀想なことではあったが「私たちは諸所に留まる先が多くあります。偏に他の人々が進むのに従って行きなさい。神様が守ってくださり必ずご無事でしょう」といい捨てて出掛けたが、憐れに思う気持ちがしばらく抑えられなかった。
一家に遊女も寝たり萩と月
(僧形の我々と同じ家に遊女たちも寝ていたというが、彼女が庭の萩なら私は空の月と、かけ離れた間柄であったよ)
曽良に語ると、書き留めてくれた。
【市振】の宿で、新潟の遊女が伴の男を返す場面。二人の女性は、それぞれに花柄の大振りな模様の衣装を着ける。一人は袖で目頭を押さえ、別れを悲しむ様子、もう一人は左手を畳に突き、右手で紙片を差し出す、意思の見える態度。紙包みは里への便りか、男への心付けか。地味な着物の男性は、笠や風呂敷包みを後ろに置き、ちんまりと坐り込んで片手で目を覆う。肩を持ち上げ、口を大きく開けて、声を出して泣いているようだ。
「黒部四十八ケ瀬」とかいうようで、数知れない川を渡って〈那古〉という浦(富山県射水市)に出る。歌枕の〈担籠(氷見市)〉は(大友家持が「藤波の影成す海の底清み沈く石をも珠とぞ吾が見る」と詠う)「藤浪」で知られるが、春でなくても初秋の趣きもまたあるだろうと、土地の人に尋ねると「ここから五里(二十キロ)磯伝いに進んで、向こうの山陰に入った所ですが、漁師の小屋が僅かにあるばかりで、旅の一夜の宿を貸してくれる者はいないでしょう」といって脅かされて、加賀の国(石川県)に入る。
わせの香や分入右は〈有磯海〉
(実った早稲の香りがする田圃道を分け入って進んでいくと、右手に歌枕に名高い有磯海が広がって見えてきた)
〈卯の花山(小矢部市)〉や倶利伽羅峠を越えて、金沢(金沢市)には七月十五日に着いた。ここに大坂(大阪府大阪市)から通う商人の何處という人がいる。彼と旅宿を共にした。
(小杉)一笑という者は、俳諧の道を好む名が少しは聞こえて、世間で知っている人もあったのに「去年の冬、早死にしてしまった」といい、その兄が追善の句会を催したので
塚もうごけ我なく声は秋の風
(葬られたその塚であってもよいから何とか動いてくれ。私が嗚咽する声は秋の風となって君の墓標を巡るよ)
ある草庵に招かれて
秋涼し手ごとにむけや瓜茄子
(秋の涼しさが気持ち良いことだ。さあ銘々に手で皮を剥いて、みずみずしいウリやナスビを味わおう)
道すがらに吟じた
あか〳〵と日はつれなくも秋のかぜ
(眩しいほどに残暑の太陽は、お構いなしに照りつけるけれど、秋の風の爽やかさに季節が感じられる)
小松(小松市)という所にて
しほらしき名や小松吹萩すゝき
(愛らしい名前だ「小松」とは。その小松が生える野原に、今は秋風が吹いてハギやススキを靡かせているよ)
この地では、太田の神社(多太神社)に詣でる。斎藤実盛の兜や錦の直垂の布があった。その昔、源氏に仕えていた頃に、源義朝から賜られたものだそうだ。確かに並の武士の持ち物ではない。兜の目庇より吹返しまで菊唐草の彫刻に金を散りばめ、龍頭には鍬形を打っている。実盛が討ち死にした後で、木曽義仲が願い状を添えてこの神社に奉納されたという由縁が、樋口次郎(兼光)が使者となったこととともに、実際に縁記に記されている。
むざんやな甲の下のきり〴〵す
(労しい思いが増してくるよ。討ち取られた実盛の首があったはずの兜の下で、キリギリスが哀れに鳴いていて)
山中温泉(加賀市)に行く途中は、白根が嶽(白山)を背後にして歩いた。左手の山際に観音堂がある。花山法皇が三十三箇所の巡礼を遂げられなさった後、観音菩薩の像を安置されて「那谷(寺、小松市)」と名付けられたそうだ。那智と谷汲とから二文字を採ったのだという。奇岩が様々に、老松を植え並べ、萱葺きの小さな御堂を岩の上に懸け造り、見事な景勝地だ。
石山の石より白し秋の風
(那谷寺の岩山の石の白さになお勝る、白秋の風の清らかさ。白山が吹き下ろすからか、観音の御堂を渡って来るからか)
温泉に浴した。その効能は有馬温泉に次ぐという。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
(山中温泉では、菊の枝を撓めて長寿の霊水となる葉の露を集めなくても、このお湯の香りで十分命が延びるよ)
主人を務める者は久米之助といって、未だ少年だ。彼の父は俳諧を好み、京都の(安原)貞室が、若かりし頃ここに来た際、心延えの至らなさを詰られて、京都に帰り(松永)貞徳の門人となってから、世間にその名が知られた。名を上げた後に、この村の人たちからは俳諧の指導料を受けなかったそうだ。今はもう昔の話となってしまったが。
曽良はお腹を患って、伊勢の国の長島(三重県桑名市)という所に所縁の者がいるので、先に発って行くとして
行〳〵てたふれふすとも萩の原 曽良
(病の身でも歩き続け、行き倒れたとしても、そこが萩の花咲く野原であったならば風雅なことさ)
と書き残した。去る者は悲しみ、残る者は愁える。(古人が「双鳧俱に北に飛び、一鳧独り南に翔る」というように)二羽の鳥が別れて雲間に迷うかのようだ。私もまた
けふよりや書付消さむ笠の露
(今日からは独り旅だ。「同行二人」と書いてある文字も消してしまうだろう、旅笠についた秋の露が)
【小松】にて、伊勢長島に向かう曽良との別れの場面。目を閉じて芭蕉に恭しく頭を下げる曽良に対し、芭蕉は慈悲深い眼差しを投げかける。「曽良は腹を病て」とのことで、そのこれからの道中が気遣われる。芭蕉の少し緩みかけた口許は、何か言葉を静かに発しているかのようだ。対座する二人の墨染め衣が長旅で萎えた風合いを、墨色の微妙な濃淡で表す。柔らかな描線が、この場のしんみりとしながらも、どこか優しい情趣を醸し出している。
大聖寺の城外(加賀市)の金昌寺(※全昌寺)という寺に泊まる。ここも加賀の国だ。曽良も前の夜に、この寺に泊まって
よもすがら秋風聞やうらの山
(一晩中、秋風の鳴る音が聞こえて寝付けなかった。裏山で吹き荒ぶ風が、心の中にも吹いている思いだった)
と残していた。(蘇東坡が「咫尺も相見ざれば、実に千里と同じ」という通り)一晩離れただけでも、千里も隔たったと同じに思える。私も秋風を聞きながら寺の宿舎に寝ると、夜明け間近、読経の声が澄み渡るほどに(食事の合図の)鐘板が打ち鳴らされて食堂に入る。「今日は越前の国へ」と、気もはやって食堂から降り下ると、若い僧たちが紙や硯を携えて、階段の下まで追い掛けてくる。ちょうど庭の柳が散ったので
庭掃て出るや寺に散柳
(御礼ばかりにお庭を掃き清めて罷り出でましょう。秋も深まり御寺でも散り始めていますよ柳の葉が)
その場で応じて、草鞋を履いたまま書き与えた。
【全昌寺】を発とうとする芭蕉を追って、若い僧たちが階段の下までやって来た。右方の僧達は四者四様の姿で、朝餉を済ませたところの和やかな様子。高名な芭蕉の評判を噂し合っているか。左方の芭蕉には、僧の一人が紙硯を差し出す。その僧の右足は裏返って足裏を見せ「追来る」の通り、走り寄って来た様を表す。口を開いて、芭蕉に一句所望の声をかける。芭蕉は聊か戸惑った表情で「とりあへぬさまして」の文意を受けた顔つきである。
越前との国境、吉崎(福井県あわら市)の入り江で舟に乗って〈汐越の松〉を訪ねた。
よもすがら嵐に波をはこばせて
月をたれたる汐こしの松 西行(※蓮如)
(夜通し吹く風が波を打ち寄せるので、月の光を映した雫を滴らせているよ、汐越の松は)
この一首で全ての光景を表し尽くしている。もし一言でも付け足す者がいたら(五本有る指にもう一本)無用の指を加えるようなものだ。
丸岡(※松岡)天龍寺(永平寺町)の長老(大夢)は、以前にご縁があったので訪ねた。また金沢の(立花)北枝という人が、気の向くままに見送ってくれて、ここまで付いて来た。所々の景勝を見過ごすことなく案じ続けて、時々に風情ある趣きの句などを聞かせた。今終に、別れに臨んで
物書て扇引さくなごりかな
(秋だからもう使わないので、句を書いた扇を二つに引き裂いて互いの形見としようと思うが、やはり名残惜しいものだ)
五十丁(五キロ半)も山門から入って、永平寺(永平寺町)を礼拝した。道元禅師のお寺だ。京都の近辺から離れて、このような山陰に事跡を遺されたのも、貴い由縁があるという。
福井(福井市)へは三里(十二キロ)ほどなので、夕飯をとってから出かけると、夕暮れで道筋が覚束ない。ここに等栽(※洞哉)という年長けた離俗の人がいる。いつの年だったか、江戸に来て私を訪ねてくれた。遥かに十年以上になる。「どんなに老いさらばえていることか、それとも死んでしまったか」と土地の人に尋ねてみると「今も存命でこの所におられます」と教えてくれた。街中のヒッソリと引き籠もったみすぼらしい小家に、夕顔や糸瓜が生えかかり、雞頭や帚木で戸口を隠している。「さてはこの家に違いない」と門を叩くと、取り繕わぬ様の女性が現れ「どちらからお出でになられた修行のお坊様ですか。主人はこの辺りの何某という方の所に行きました。もし御用がおありでしたらお訪ねなさってください」という。「彼の妻に違いない」と知られた。「古典の物語にも、こんな場面があったな」と思いつつ、やがて尋ね当てて、彼の家に二晩泊まって「中秋の名月は、敦賀の港(敦賀市)で愛でよう」と旅立った。
【福井】で等栽宅を訪ねる場面。「夕貌へちまのはえかゝりて鶏頭はゝ木ゞに戸ぼそをかくす」怪しげな小家と記す文に合わせ、草木が生い茂る茅屋を描く。「門を扣ば」の通り、画中の芭蕉も戸板に向けて拳を上げている。蔀戸を上げた窓内に女性が顔を覗かせるが「侘しげなる女」の風とまでは見えない。墨と茶色とに囲まれた中に現れる、女性の緑色の衣装がハッと目を惹く効果をもたらし、芭蕉の視線の動きが観る者にも伝わる。
等栽も「一緒にお送りしましょう」と、衣の裾を気取って捲り上げ「道案内を」と浮かれ立って行く。
やがて白根が嶽(白山)は見えなくなり、比那が嵩(日野山)が見えて来た。歌枕の〈あさむつの橋(福井市)〉を渡り〈玉江の芦(前同)〉は穂が出ていた。〈鶯の関(南越前町)〉を過て、湯尾峠(前同)を越えると(木曽義仲所縁の)燧が城。〈かへる山(帰山)〉に初雁の音を聞いて、八月十四日の夕暮れ、敦賀の港で宿を求めた。
その夜、月が格別晴れ渡った夜空に見えた。「明日の十五夜もこのように晴れるものかな」というと「北陸によくあることで、やはり明晩の晴れか曇りかは予測できません」と、亭主に酒を勧められて、けいの明神(氣比神宮、敦賀市)に夜参りした。仲哀天皇をお祀りする。社頭は神々しく、松の木の間から月光が差し込んで、神前の白砂は霜を置いたように輝く。「昔のこと(時宗の)遊行二世の(他阿)上人が大願を発起されたことがあって、自ら草を刈られ、土や石を運ばれ、泥濘を乾かしてくださったので、参詣に行き来するのに困りません。この先例が今にも廃れず、代々の上人が神前に砂を運んでくださいます。これを『遊行の砂持ち』と申しております」と亭主が教えてくれた。
月清し遊行のもてる砂の上
(月の光も清らかに照らして称えているよ。遊行上人が手ずから運ばれた神前の白砂の上で)
八月十五日、亭主の言葉に違わず雨が降った。
名月や北国日和さだめなき
(中秋の名月が雲の向こうに出ているだろう。北陸の天気は変わりやすく、今夜は生憎、雨となってしまったが)
八月十六日、空が晴れたので(西行が「汐染むるますほの子貝拾ふとて色の浜とは言ふにやあらなむ」と詠んだ)「ますほの小貝」を拾おうと、種の浜(色浜)へ舟を走らせる。海上で七里(二十八キロ)あった。天屋何某(室五郎右衛門)という人が、重箱や酒筒などを気遣って支度させ、世話する者を多く舟に乗せてくれて、追風に束の間吹かれて到着した。
浜には僅かに漁師の小屋があり、侘しい日蓮宗の寺(本隆寺)があった。そこで茶を飲み、酒を温めながら、夕暮れの寂しさにしみじみ感じ入った。
寂しさや須摩にかちたる浜の秋
(寂しいとは当にこのことだ。光源氏が侘び住まいした須磨の浦より勝っているよ、色の浜の秋の夕暮れは)
浪の間や小貝にまじる萩の塵
(波が打ち寄せる合間に汀を見てみると、小振りな貝に混じって、散った萩の小さな花弁が流れ着いていたよ)
その日の出来事の大凡は、等栽に記させて寺に残した。
門下の(八十村)露通(路通)もこの港まで出迎えてくれて、美濃の国へと同行した。馬に乗れて助かった思いで大垣の庄(大垣市)に入ると、曽良も伊勢から来て再会し(越智)越人も馬を走らせて来て(近藤)如行の家に入り、皆で集った。(津田)前川さんや(宮崎)荊口親子、その他の親しい人々が昼も夜も訪ねてくれて、まるで甦った者に会うかのように、喜んだり労ったりしてくれる。
旅の疲れも未だ癒えないのに、九月六日になるので「伊勢神宮の遷宮を拝もう」と、また舟に乗って
蛤のふたみにわかれ行秋ぞ
(離れ難いハマグリの蓋と身とを分けるように、二見浦に向かって貴方たちと別れて行く、ちょっと寂しい秋だなあ)
【大垣】で、門人近藤如行の宅に知己が集って芭蕉を労る場面。中央の芭蕉の後ろで肩を叩くのは、如行の弟子竹戸。芭蕉は、その按摩で疲れが癒やされたことを喜んだ。画中でも、竹戸は明るい色合いの衣装で目を惹くように描かれ、その働きぶりを蕪村も賞している。微笑んだ芭蕉の表情に象徴される通り、朗らかな雰囲気の一座の様子が長旅の大団円を告げる。蕪村が、ラストシーンに和やかな場面を与えたのは、本作のみの趣向である。
右の奥の細道上下二巻は(黒柳)維駒さんの求めに応じ、京都夜半亭の静かな窓辺で写したものだ。
時に安永八年(一七七九)冬十月
六十四翁蕪村
奥の細道画巻 第二巻 俳句索引
【あ】
あか〳〵と日はつれなくも秋のかぜ
秋涼し手ごとにむけや瓜茄子
暑き日を海にいれたり最上河
あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ
蜑の家や戸板を敷て夕すゞみ 低耳
あらうみや佐渡によこたふ天河
有がたや雪をかほらす南谷
石山の石より白し秋の風
【か】
語れぬ湯どのにぬらす袂かな
象潟や雨に西施がねぶの花
きさがたや料理何くふ神祭 曽良
蚕飼する人は古代のすがたかな 曽良
雲の峰いくつ崩て月のやま
けふよりや書付消さむ笠の露
【さ】
寂しさや須摩にかちたる浜の秋
さみだれをあつめてはやし最上河
しづかさや岩にしみ入蝉の声
しほこしや鶴はぎぬれて海涼し
しほらしき名や小松吹萩すゝき
すゞしさやほの三か月の羽黒山
涼しさを我宿にしてねまるなり
【た】
塚もうごけ我なく声は秋の風
月清し遊行のもてる砂の上
【な】
波こえぬ契ありてやみさごの巣 曽良
浪の間や小貝にまじる萩の塵
庭掃て出るや寺に散柳
のみしらみ馬の尿するまくらもと
【は】
這出よかひやか下のひきの声
蛤のふたみにわかれ行秋ぞ
一家に遊女も寝たり萩と月
ふみ月や六日も常の夜には似ず
【ま】
まゆはきをおもかげにして紅の花
むざんやな甲の下のきり〴〵す
名月や北国日和さだめなき
物書て扇引さくなごりかな
【や】
山中や菊はたおらぬ湯の匂
行〳〵てたふれふすとも萩の原 曽良
ゆどの山銭ふむ道の泪かな 曽良
よもすがら秋風聞やうらの山
【わ】
わせの香や分入右は有磯海